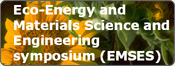教育活動
GCOE教育ユニットカリキュラムの実施
GCOE教育ユニット及びCO2ゼロエミッシション教育プログラムの運用
教育ユニットの運用と教育プログラムの提供を平成21年4月から本格的に開始した。教育ユニットに73名の学生が参加登録し、CO2ゼロエミッション教育プログラム科目を履修すると共に、RA/TAへの採用、研究発表旅費の助成、教育プログラム科目「国際エネルギーセミナー(グループ研究)」履修者に対する研究経費等の研究支援を受けることができた。以下に教育ユニットの概要と主要な教育プログラム科目の内容を示す。
教育ユニット参加登録資格者
エネルギー科学GCOE教育ユニットに参加登録できる学生は,以下の研究科・専攻に在籍する博士後期課程の学生である
・エネルギー科学研究科
エネルギー社会・環境科学専攻
エネルギー基礎科学専攻
エネルギー変換科学専攻
エネルギー応用科学専攻
・工学研究科
原子核工学専攻
教育ユニット参加登録者に対する研究支援
- 教育ユニットに参加登録した者は,GCOEのRAあるいはTAとして採用される資格を得る。
- 教育ユニットに参加登録した者は,研究発表のための旅費に対する助成を受けることができる。
- 教育プログラム科目「国際エネルギーセミナー(グループ研究)」履修者については,グループ別に提出された研究計画書に基づき,必要な研究経費を一人当たり年間最大150万円まで支援する。
III.CO2ゼロエミッション教育プログラム
教育ユニットに参加登録し,履修期間内に下記の科目から計14単位以上(内,必修9単位)を取得した者を教育プログラム修了者と認定し,修了認定証を発行する。以下に各科目の単位数と平成21年度の履修者数(平成22年1月末現在)を示す
- 国際エネルギーセミナー Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ(各2単位,必修4単位,最大8単位)
7―8名のグループに分かれてCO2ゼロエミッションエネルギー社会について問題解決学習法(PBL)に基づく英語によるグループ討論を中心に学習を進め,国際社会で実践的に役立つ能力を習得する。
履修者:Ⅰ(前期)58名,II(後期)67名 - 最先端重点研究 I,II(各1単位,必修2単位)
エネルギーシナリオ策定研究と有機的に連携をとりながら,シナリオの実現性を評価するエネルギー社会・経済研究と化石資源に依存しない先進エネルギー技術の開発研究を行う。多彩な環境調和型エネルギー基礎研究・要素技術を統合した,「エネルギー社会・経済研究」,「再生可能エネルギー(太陽光エネルギー,バイオマスエネルギー)研究」および「先進原子力エネルギー研究」を推進し,その成果をもとにしたCO2ゼロエミッションエネルギーシナリオ策定に関する研究を行う。
履修者:Ⅰ(前期)36名 -
フィールド実習 (必修2単位)
1.学内実習
低出力の小型原子炉である京都大学臨界実験装置(KUCA)を用いた基礎的な原子炉物理に関する実験課題に取り組み,さらに受講生全員を対象とした原子炉の運転実習を行う。実習は3日間で,初日は保安教育・施設見学・原子炉物理の講義,2日目は原子炉の動特性実験(制御棒反応度測定),3日目は原子炉の運転実習を行う。
2.学外実習
原子力発電所の見学,運転シミュレータによる運転実習を通じて原子力発電所の仕組みや安全性について習得する。また,原子力発電所における地域共生活動の内容,課題,今後の展望などを実地に学習する。
履修者:26名
-
研究発表 Ⅰ,II,III (各1単位,必修1単位,最大3単位)
学会などにおける研究発表,履修者:年度末に集計
-
海外研修 (1~4単位)
国際機関での研究,研修,履修者:年度末に集計 -
英語による授業 (半期:2単位,1/4期:1単位)
履修者:24名
IV.フィールド実習
- 目的
- この実習では原子力システムや原子力発電所等、社会と緊張関係を持つ場における課題等を実地に学習する。
- 内容
- (1)京都大学原子炉実験所
平成21年8月26日~28日の3日間にわたって実施され,13名が参加した.内容は,臨界実験装置(KUCA)を用いた基礎的な原子炉物理実験と運転実習であり,保安教育,原子炉物理講義,制御棒校正講義に引き続いて,原子炉の動特性実験(制御棒校正実験、臨界近接実験)行い,最後にKUCAの運転実習を全員で行い,レポート作成・討論会を開催した。
 |
 |
|
| 原子炉実験所・臨界実験装置(KUCA) | KUCA制御室にて |
- 関西電力原子力事業本部(美浜)および高速増殖原型炉「もんじゅ」(敦賀)
- 平成21年11月20日,21日の2日間にわたって開催され,10名が参加した.関西電力原子力事業本部では,原子燃料サイクルの課題,原子力発電施設の耐震安全性,福井県における地域共生活動について講義を受けた後,意見交換を行った.日本原子力研究開発機構・高速増殖原型炉「もんじゅ」では,もんじゅおよびナトリウム研修施設を見学した後,運転シミュレータ操作方法の講義および通常操作訓練・異常事象発生時の対応訓練を受け,意見交換を行った.
 |
 |
|
| 関西電力原子力事業本部での受講風景 | 関西電力原子力事業本部にて |
海外研修
海外研修においては,国際機関をはじめとする海外での研究,研修に対して単位が認められる.今年度はその一環として,GCOEカリキュラム委員会からの支援を受けて,エアランゲン–ニュールンベルグ大学(ドイツ)で開催された第3回先進エネルギーと材料に関する京都エアランゲンシンポジウムでの研修が行われた.全参加者約50名の内,京大からの参加者は16名であり,GCOE教育ユニットの学生6名に加えて,それ以外の京都大学学生4名が参加した.平成21年9月3日~4日に開催されたシンポジウムに先立ち,9月1日にはバイエルン応用エネルギー研究センター,エアランゲン大学材料科学科研究室を,翌2日にはカールスルーエ研究センターを見学した.シンポジウムでは全体で29件が口頭発表され,活発な議論が行われた。
国際サマースクール
平成21年8月20日~21日に京都大学百周年時計台記念館で開催されたGCOE国際シンポジウム "ZERO CARBON ENERGY Kyoto 2009" に併せて,エネルギー科学国際サマースクールが8月20日~22日の3日間にわたって開催された.シンポジウムでの講演に加えて,8月20日には時計台記念館にてポスターセッションが開催され,計49件の発表が行われた.さらに,8月22日には京大会館にてオーラルセッションが開催され,計21件が2つの会場で発表された.各セッションではGCOE教育ユニット運営委員会委員による選考により,ポスター発表賞2名,オーラル発表賞2名が選ばれた。
本国際サマースクールにはGCOE教育ユニットの学生と若干名の国内他大学からの参加者に加えて、中国、韓国及びデンマークから20名を越える参加があった.GCOE教育ユニット学生の出身国自体が、中国、韓国に加え、北アメリカ、アフリカ、アジア、ヨーロッパなどからの12カ国に亘っており,国際色豊かなサマースクールとなった.なお,オーラルセッションでの座長はGCOE教員が担当したが、その他に関してはすべてGCOE教育ユニット学生により運営された。
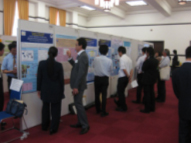 |
 |
|
| ポスターセッション風景 | オーラルセッション風景 |
日韓大学院生合同シンポジウム
日韓大学院生の国際エネルギー科学教育を推進するため,韓国アジョウ大学との協力でエネルギー科学に関する日韓大学院生合同シンポジウム(2010 Kyoto-Ajou Graduate Student Joint Symposium on Energy Science)が,平成22年2月2日におうばくプラザにて開催された.韓国アジョウ大学からBK21プログラムの一環として院生13名,教員8名が来学し,日本側からはGCOE教育ユニット所属院生22名と関連教員10名が参加した.シンポジウムでは韓国側から11件,日本側から9件の院生による口頭発表が行われ,エネルギー科学に関する活発な議論が交わされた.今回のシンポジウムにおいても,GCOE教育ユニットの学生がプログラム企画、案内、韓国側との調整を進め,当日の司会、会場設営、運営等も学生が主体的に行った.シンポジウム後の懇親会においても日韓学生の交流が活発に行われた。
 |
 |
|
| シンポジウム風景 | ||
学生の学会派遣
2009年度は、のべ96名の学生を54の国内外の学会や国際会議などへ派遣した。
RA/TAプログラム
RA候補者を,以下の評価要領により5名の審査員により評価し,5名の合計点で採否をきめた。特に上位のものを特別時間単価で採用した。2009年度は、RA 32名(内6名は後期から)とTA4名を採用した。その内,特別時間単価によるRAの採用は9名である。
評価要領:各項目25点満点で合計100点満点。
- 本GCOEプロジェクトへの貢献度
- 当該分野における学術としての重要度と達成度
- 研究の将来性と総合評価
- 研究実績
(研究実績については,学年(研究を始めてからの年数)を考慮)