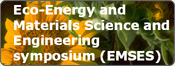21COEの成果と発展
エネルギー科学研究科とエネルギー理工学研究所は、平成14年度から5年間にわたり21世紀COEプログラム「環境調和型エネルギーの研究拠点形成」(E11)を共同で実施し、以下のように所期の成果を得た。
太陽エネルギータスクでは、超階層ナノ構造素子という京都大学独自の概念の基に新規有機太陽電池が認知され、NEDO未来型太陽電池の目標に採用された。また将来の基幹エネルギーとして重要な核融合研究としてヘリオトロンJ、球状トカマクにおける先進プラズマの研究を進めるとともに、核融合炉等の先進エネルギープラント用高Cr酸化物分散強化鋼やSiC複合材の開発や高温ブランケットとバイオマスからの水素製造などの画期的なエネルギー変換システムを提示し、経産省及び文科省の国家プロジェクトへと発展している。水素エネルギータスクでは水素貯蔵媒体をアンモニアとする独自のアンモニアサイクルを提唱し、新しい溶融塩電解技術を発明するとともに、一室型燃料電池の開発や水素エンジンでの世界最高効率の41%を達成した。一方、バイオエネルギータスクでは、京都大学独自の超臨界流体技術によるバイオ燃料製造プロセスを確立し、CO2ゼロエミッション型バイオエネルギーの生産・利用による、今後の低環境負荷エネルギー利用システムの構築に明確な方向付けがなされた。トータルエネルギー評価タスクでは,新しい評価手法を開発すると共に、「2030年エネルギー需給シナリオ」を策定し、2030年にCO2の50%削減の可能性を発表し、わが国エネルギー政策へインパクトを与えた。
- 太陽エネルギー:有機薄膜太陽電池で効率4.1%を達成,小型軽量 位相制御マグネトロン開発、球状トカマクや先進炉材料開発
- 水素エネルギー:アンモニアサイクル、1室式燃料電池、水素エンジン開発
- バイオエネルギー:超臨界メタノール法によるバイオディーゼル燃料
- トータルエネルギー評価:継承可能なデータベース、2030年エネルギー需給シナリオ
学術論文916編、著書110冊、基調講演184件、特許124件
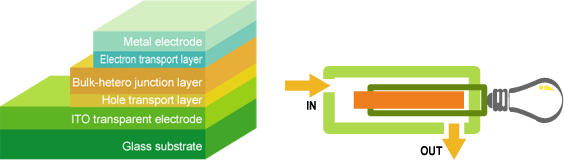
- 国際エネルギースクール・RA,TAへの採用
- 公募型研究・テキスト刊行 (和文・英文)
ASEAN COST+3 会議、Asian COREへ

- 外拠点(タイ)・SEEフォーラムの発足
- 市民講座の開催(47都道府県)
- 国際(5回)・国内(3回)シンポジウム開催
A大学(8名)、公的研究機関(16名)、企業(8名)、PD(33名)を輩出

各技術開発間の融合性、原子力エネルギー、政策への反映、東南アジア諸国に対する人材育成